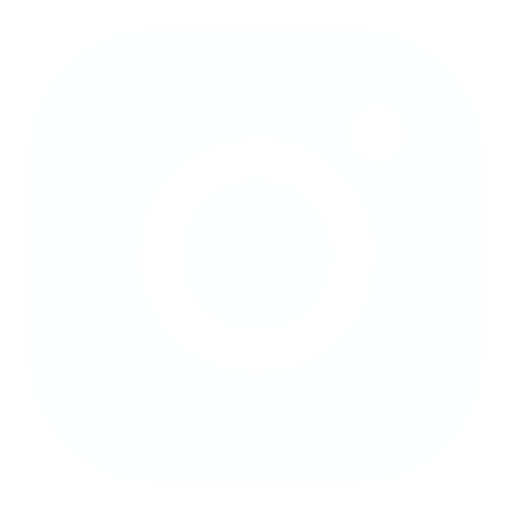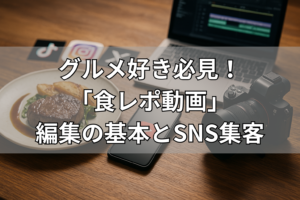副業、個人事業を始め利益が増えていくと確定申告をする必要が出てきます。
確定申告とは何か?

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間に得た所得を自分で計算し、納めるべき所得税を国に申告・納付する手続きです。会社員の年末調整でカバーされない副業収入や医療費控除、住宅ローン控除などを利用する場合には必須となります。具体的には、収入から必要経費や各種控除を差し引いて課税所得を算出し、源泉徴収された税額との差額を申告書に記入して納付または還付を受けます。申告書は国税庁のe-Tax(電子申告)や紙の様式で作成可能で、初めてでも会計ソフトやスマホアプリを使えばスムーズに進められます。
所得税は累進課税のため、所得が増えるほど税率も高くなります。個人事業主やフリーランスだけでなく、アルバイト収入が20万円を超えた会社員も申告対象となることがある点にご注意ください。また、青色申告特別控除や白色申告制度により控除額が異なるため、ご自身の状況に合った申告方法を選ぶことが大切です。初めての確定申告は不安がつきものですが、国税庁公式サイトや市町村の税務相談窓口を活用することで安心して手続きを進められます。
確定申告が必要な人は?

確定申告は、以下のいずれかに該当する方が原則として必要です。
- 給与所得以外の所得が20万円超
副業で得た報酬、家賃収入、株や仮想通貨の譲渡益など、事業所得・雑所得・譲渡所得が合計20万円を超える場合。 - 年収が2,000万円超の給与所得者
1カ所からの給与収入が2,000万円を超えると、年末調整だけでは済まず申告が必要です。 - 医療費控除・寄附金控除を受けたい人
医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税など)は、確定申告を行うことで税金が還付されます。 - 青色申告の承認を受けている事業者
青色申告承認申請書を提出済みの個人事業主は、65万円控除などを受けるために毎年申告が必要です。 - 退職所得以外の収入がある2ヵ所以上で働く人
複数の会社から給与を得ていると年末調整が各社で完結せず、合算した申告が求められます。
その他、山林所得・一時所得など特殊な所得がある場合も申告義務が発生します。事業収支や控除の状況は人それぞれですので、不安なときは会計アプリでシミュレーションするか、税務署・税理士にご相談ください。
申告期間と期限

所得税及び復興特別所得税の確定申告は、毎年1月1日~12月31日の所得を対象に、翌年2月16日~3月15日の間に行います。この期間内に申告書を提出し、納税も同時に完了させることが必要です。電子申告(e-Tax)は24時間受付され、マイナンバーカード方式やID・パスワード方式で利用できますが、システムメンテナンス時間には注意が必要です。紙提出の場合は郵送の消印有効、税務署窓口への持参は各署の受付時間内に限られます。なお、個人事業者の消費税及び地方消費税の申告期限は3月31日までです。提出期限を過ぎると無申告加算税などのペナルティが発生しますので、余裕をもって手続きを進めましょう。
準備すべき書類一覧

以下の書類をあらかじめそろえておくと、確定申告がスムーズに進みます。
本人確認書類
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- または、通知カード+運転免許証・パスポートなどの写真付き身分証明書
収支・所得を証明する書類
- 源泉徴収票(給与所得者用)
勤務先が年末調整後に発行する書類で、その年に支払われた給与の総額や差し引かれた所得税額が記載されています。給与所得者が確定申告を行う際には、課税所得の根拠資料として必ず必要です。 - 支払調書(報酬・契約金などを受け取った場合)
フリーランスや個人事業主がクライアントから受け取る報酬について、支払った側(企業や個人事業主)が作成・提出する書類です。年間に支払われた業務委託料や原稿料などの金額と源泉徴収税額が明記され、雑所得や事業所得の計算根拠となります。 - 事業所得者向け帳簿・領収書・請求書など
個人事業主やフリーランスは、日々の取引を「帳簿」(収入・経費を記録した台帳)に記載し、経費として計上する根拠となる領収書や、売上を証明する請求書を保存する必要があります。青色申告を行う場合は複式簿記による帳簿付けが求められ、正確な記録が65万円控除などの優遇措置の適用条件になります。
各種控除の証明書
- 医療費控除:医療機関発行の領収書一式
- 生命保険料控除:保険会社発行の控除証明書
- 地震保険料控除:保険会社発行の控除証明書
- 小規模企業共済等掛金控除:掛金払込証明書
- 寄附金控除(ふるさと納税など):寄附先発行の受領証
これらを整理・ファイリングし、電子申告(e-Tax)の場合はスキャンまたは写真データで保管しておくと安心です。
申告方法の選択肢

確定申告には大きく分けて
- 「e-Tax(電子申告)」
- 「書面申告」
の2通りがあります。
それぞれメリット・注意点が異なるため、自分の状況や好みに合わせて選びましょう。
e-Tax(オンライン申告)のメリット・手順
メリット
- 自宅から24時間申告可能:税務署窓口の営業時間を気にせず申告できます。
- ペーパーレス化で書類管理が楽:添付書類(控除証明書など)を入力のみで提出でき、原本提出が不要になる場合があります。
- 還付が早い:郵送申告より3週間ほど早く還付金が振り込まれるケースが多いです。
利用前の準備
- マイナンバーカード方式:スマホまたはICカードリーダーが必要。
- ID・パスワード方式:事前に税務署で「利用者識別番号」と「暗証番号」を取得します。
基本的な手順
- 国税庁「確定申告書等作成コーナー」にアクセスする
- e-Tax用に入力画面で源泉徴収票や医療費控除などの情報を入力
- マイナンバーカードを使って電子署名(またはID・パス方式でログイン)
- 送信ボタンを押して完了(送信後に受付結果がメール等で届きます)
書面申告(税務署窓口・郵送)の流れ
メリット・デメリット
- メリット:スマホやICリーダーが不要、画面操作に慣れていない方でも安心。
- デメリット:税務署の営業時間内に出向くか、封筒・切手を用意して郵送が必要で、処理に時間がかかる場合があります。
基本的な手順
- 申告書を入手
- 税務署窓口で直接入手
- 国税庁サイトからPDFをダウンロード・印刷
- 必要事項を手書きまたはパソコンで入力
- 青色申告決算書や収支内訳書がある場合は別表も用意
- 申告書に署名・捺印
- 本人確認書類の写しを同封(e-Taxと同様にマイナンバー確認のため)
- 税務署へ提出
- 窓口:受付時間内に持参
- 郵送:消印有効期間内に発送
どちらの方法を選んでも、2月16日~3月15日の申告期間内に提出・送信することが必須です。
e-Taxなら時間の制約が少なく、還付のスピードも速いので、PC・スマホ環境が整っている方には特におすすめです。
補足:事業規模別!経費として扱える費用例 徹底解説!

副業(会社員が動画編集/SNS運用を副業する場合)
- ソフトウェア利用料
Premiere Pro や After Effects、Canva Pro などの月額サブスクリプション - 通信費
動画素材アップロード/SNS投稿のためのモバイル回線・光回線(業務分按分) - 外注料
テロップ作成やサムネイル制作をクラウドソーシングで依頼した際の報酬 - ストック素材費
有料の映像素材(Envato Elements など)やBGMライセンスの購入費 - 機材消耗品費
SDカードや外付けSSD、マイクの風防、カメラのバッテリーなど10万円未満の消耗品 - カフェ代/会議費
クライアント打ち合わせ時の飲食費(小規模な打ち合わせに限定)
個人事業主(フリーランス動画クリエイター/SNSコンサルタント)
- 機材減価償却費
10万円以上のカメラ、PC、モニタ、編集コントローラー類を数年で按分 - 事務所家賃・光熱費の按分
自宅の一部を編集スペースとして使う割合に応じた家賃・電気・水道代 - 広告宣伝費
Instagram・YouTube広告の配信費用、WebサイトのSEO対策費用 - 外注費
アニメーション制作やコピーライティング、SNS運用代行の委託料 - クラウドサービス利用料
Google Workspace、Dropbox Business、動画共有プラットフォームのプレミアム料金 - 研修・セミナー費
動画編集講座やSNSマーケティングセミナーの受講料
法人(動画制作会社/SNSマーケティング会社)
- 役員報酬・社員給与
編集スタッフやSNS運用担当の給与・賞与・社会保険料 - オフィス賃借料・共益費
撮影スタジオや編集室を含む事務所スペースの賃料・管理費 - 減価償却費
業務用スタジオ機材(照明機器、カメラセット)、サーバー、業務用PCの耐用年数に応じた償却費 - 広告・宣伝費
クライアント向けプロモーション動画制作費、Web広告・SNS広告の運用費 - 交際接待費
取引先とのビジネスランチや業界イベントでの懇親会費用(上限規定あり) - 教育訓練費
社員向けのAdobeソフトトレーニングやマーケティング研修の受講料 - 旅費交通費
撮影ロケ地への出張旅費・交通費・宿泊費
いずれも「業務(事業)遂行のために直接必要」な支出であることが前提です。
按分や減価償却のルール、交際費の損金算入限度額など、詳細は国税庁サイトや会計ソフトのガイドを参照してください。
失敗しないポイントは習慣作りに!

初めての確定申告をするとき、事前準備が足りずに提出直前で慌てて準備。結局漏れがあって追徴課税されてしまうなんてことも。そんなことにならないためのポイントを紹介します。
収支は即アプリに入力


スマホ会計アプリ(freee/マネーフォワードなど)に、入出金が発生したらその場で記録。レシートを写真で撮って自動読み込みすると管理がスムーズです。
領収書は月ごとにファイリング

紙の領収書は「月別・用途別」にクリアファイルや封筒にまとめ、PDF化してクラウド保存しておくと、探す手間がゼロになります。
プライベートと事業用口座を分ける

銀行口座・クレジットカードを“事業用”と“個人用”で分けると、収支の切り分けが明確になり帳簿付けがラクに。
交通費・出張経費はこまめにメモ

毎回の移動距離や乗車区間、出張先で使ったタクシー代などをスマホのメモアプリに記録。後でまとめて申告用資料が作れます。
経費になりそうな支出を意識的にチェック

書籍購入、研修費、文具・ソフトウェアの購入など、業務に関係する支出は「経費かも?」と立ち止まって領収書を保管しましょう。
控除対象の情報はカレンダーに登録

医療費・寄附金・保険料など、控除証明書が届く時期をカレンダー登録しておくと、見落としが防げます。
定期的に帳簿残高をチェック

月末にアプリやエクセルで残高を確認し、「金額にズレがないか」「未入力がないか」を点検すると、申告前の突発対応が減ります。
クラウドストレージでの自動バックアップ

領収書PDF・帳簿データ・申告書類はGoogle DriveやDropboxに自動同期。データ紛失リスクを下げられます。
補足:青色申告と白色申告の違いとメリット・デメリット

個人事業主やフリーランスが選べる「青色申告」と「白色申告」は、主に帳簿付けの方法と節税効果に違いがあります。
青色申告
- 記帳方法:原則として複式簿記で帳簿を作成し、貸借対照表・損益計算書を添付します。
- 特別控除:最大65万円(または55万円・10万円)の青色申告特別控除が受けられます。
- 損失繰越:事業で損失が出た場合、翌年以降3年間にわたり損失を所得から差し引けます。
- 家族従業員給与:生計を一にする配偶者や親族への給与を必要経費に計上可能です。
- 電子帳簿保存・e-Tax特典:電子申告や電子帳簿保存を行うと追加の要件緩和が受けられます。
メリット
- 大幅な節税(65万円控除+繰越控除)
- 事業専従者給与の経費化
- 電子申告で手続き簡略化
デメリット
- 複式簿記による記帳が煩雑
- 青色申告承認申請書を事前提出が必要
- 毎年貸借対照表・損益計算書の作成が必須
白色申告
- 記帳方法:簡易的な単式簿記でOK。確定申告書と収支内訳書を提出します。
- 控除:特別控除はありませんが、令和2年分から簡易帳簿保存を行えば10万円控除を受けられる場合があります。
- 損失繰越:原則できません(一部例外あり)。
メリット
- 記帳や提出書類がシンプル
- 青色申告への切り替え申請が不要
デメリット
- 節税効果が限定的
- 損失繰越や家族給与の経費化ができない
どちらを選ぶかは、事業規模や帳簿付けの手間、節税ニーズによって判断します。
「節税効果を最大化したい」「事業が軌道に乗っている」なら青色申告が有利です。一方、「登録だけで簡単に済ませたい」「副業レベルの収入」に留まる場合は白色申告で問題ありません。
よくある申告ミスと防止策
確定申告でよく起こるミスと、その防止策をまとめました。事前に対策を講じておくことで、申告期限直前の慌てやペナルティを回避できます。
- 経費の計上漏れ・認識不足
- ミス例:業務に必要な書籍購入費や交通費を経費に含め忘れる
- 防止策:日々の支出を即入力できるクラウド会計アプリを活用し、「経費かも?」と思ったらレシートを即スキャン。月末に未登録がないか振り返る習慣をつけましょう。
- 控除書類の紛失・未取得
- ミス例:医療費控除証明書や生命保険料控除証明書を紛失して申請できない
- 防止策:控除証明書は発行されたらすぐにスキャンまたは写真撮影し、クラウドストレージに保存。カレンダーアラートで発行時期を通知することで漏れ防止になります。
- 帳簿付けの不備(数字の食い違い)
- ミス例:収入合計と通帳残高が合わない、入力ミスによる残高ズレ
- 防止策:毎月末に「入金合計=売上合計」「出金合計=経費合計」になるかチェックリストで確認。自動仕訳機能を使いつつ、月1回は手動で残高照合を行いましょう。
- 申告方式の選択ミス
- ミス例:e-Tax利用の準備不足で書面申告に変更し忘れ、提出期限を過ぎる
- 防止策:申告方式は1月末までに決定し、マイナンバーカードや利用者識別番号の取得手続きを完了させる。e-Taxのメンテナンス期間を事前に確認し、代替手段も用意しておきましょう。
- 提出書類の同封漏れ
- ミス例:控除証明書の原本や本人確認書類のコピーを同封し忘れ、再提出を求められる
- 防止策:提出前に「必要書類チェックリスト」を用意し、印鑑、マイナンバー、控除証明など8項目程度を一つずつチェック。書面・郵送時の同封リストも作成すると確実です。
- 期限ギリギリ申告によるトラブル
- ミス例:申告期限当日になって帳簿不整備やシステム障害で提出できない
- 防止策:少なくとも申告期間の前半(2月末)には申告書の作成を終え、余裕をもって送信または提出。提出後は必ず受信通知や受領書を保管してください。
これらの防止策を日常のルーティンに組み込むことで、申告ミスのリスクを大幅に減らせます。チェックリストやクラウドツールを活用し、ストレスフリーな確定申告を目指しましょう。
よくあるQ&A

Q1 副業収入が年間20万円未満なら確定申告は不要ですか?
A1 副業など給与所得以外の合計所得が20万円未満であれば、原則として確定申告は不要です。ただし、医療費控除や住宅ローン控除を受ける場合は申告することで税金が還付されますので、控除目的で申告するとお得です。
Q2 年の途中で退職・転職した場合、確定申告はどうすればいい?
A2 退職後に源泉徴収票が2社以上から発行される場合や、年末調整を受けていない場合は自分で合算し申告が必要です。転職先で年末調整を受けられれば申告不要となるケースもありますので、勤務先へ確認しましょう。
Q3 医療費控除の申請手順は?
A3 医療費の領収書を集め、年間10万円(所得の5%のいずれか低い額)を超えた部分を申告します。明細書の作成が簡単になる「医療費控除の明細書フォーマット」は国税庁サイトでダウンロード可能です。
Q4 e-Taxと書面申告、どちらが向いていますか?
A4 PCやマイナンバーカードがあればe-Taxが便利です。24時間申告・還付が早いメリットがあります。スマホやICリーダーがない場合は、紙の申告用紙を印刷して窓口または郵送で提出しましょう。
Q5 青色申告を初めて行うには何が必要?
A5 青色申告承認申請書を毎年3月15日までに税務署へ提出し、複式簿記で帳簿を付ける必要があります。65万円控除を受けたい場合は、正規の簿記記帳と貸借対照表の添付も忘れずに行ってください。
これらの公式サイトや信頼性の高い解説を参考に、最新の情報で手続きを進めましょう。
おわりに

本記事では、初めての確定申告に必要な基礎知識から申告方法、準備書類、e-Taxや会計アプリの活用、失敗を防ぐポイント、Q&Aまでを網羅的にご紹介させて頂きました。確定申告は慣れない作業で不安が大きいものの、早めの書類収集とクラウド会計ツールの併用、申告方式の選択を適切に行うことで、手間と時間を大幅に削減できます。また、疑問が生じたら国税庁公式サイトや税務署相談コーナーを活用し、安心して手続きを進めましょう。
申告期間中(2月16日~3月15日)は例年混雑が予想されますので、今回ご紹介したスケジュールを参考に、1月中旬から2月中旬にかけて準備を完了させることをおすすめします。提出後は受付確認を必ず行い、控えは来年以降の申告時にも役立つので大切に保管しておきましょう。
初めての確定申告を無事終えることは、大きな達成感につながります。ここで培った効率的な帳簿管理やデータ保管の習慣は、翌年以降どんな事業規模でも役に立つはずです。ぜひ本記事をガイドとして活用し、安心かつスマートに申告を完了させてください。次のステップとして、青色申告承認や節税対策にもぜひ挑戦してみましょう。
参考サイト・URL一覧
- 国税庁 確定申告書等作成コーナー
動画チュートリアル付きで申告書を作成できる公式ページ - 国税庁 申告が必要な方
確定申告の対象者をチェックできる解説ページ - 国税庁 e-Tax
電子申告システムの利用案内とメンテナンス情報 - 国税庁 医療費控除の明細書
医療費控除の申請に必要な明細書フォーマットをダウンロード - freee「確定申告の必要書類まとめ」
会計ソフトfreeeによる必要書類一覧と解説 - マネーフォワード「確定申告のやり方と流れ」
マネーフォワードBizで学ぶ申告手続きのステップ - 国税庁 青色申告の手引き
青色申告承認申請から65万円控除まで詳しく解説 - 国税庁 消費税及び地方消費税の申告
個人事業主向け消費税申告の期限と手続き - 国税庁『はじめてみませんか?青色申告』
- 弥生『青色申告と白色申告の違い』